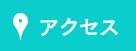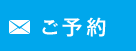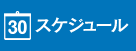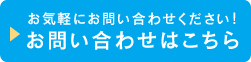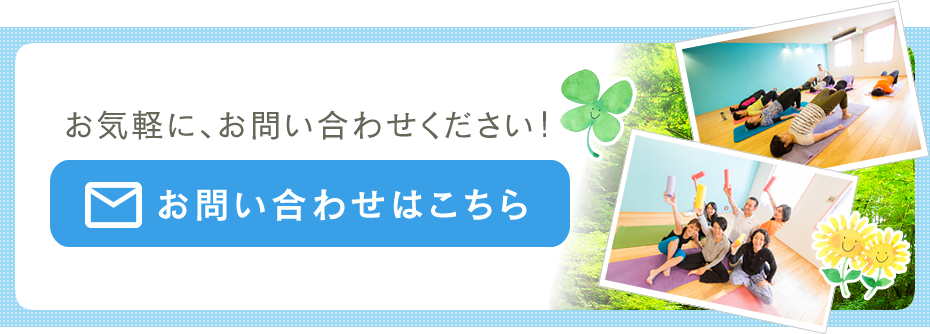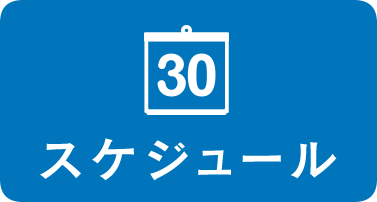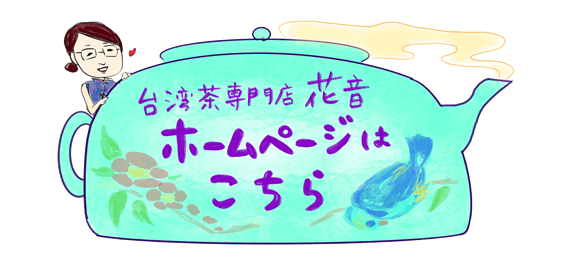脚を組んだら骨盤が歪む? | 福岡の大濠にあるピラティス・ヨガ スタジオKANON(カノン)
代表ブログ
身体のこと
脚を組んだら骨盤が歪む?
椅子に座ると、つい脚を組んでしまう。
これ、「骨盤が歪むから良くない」と聞いたことはありませんか?
けど、その“歪み”は、実際には何を意味しているのでしょう。
レッスンの中でも、「私、よく脚を組んでしまうんです。ダメですよね?」とおっしゃる方がいます。
「脚を組む癖のせいで骨盤が歪んでいると指摘されたことがある」という方も。
この“歪み”という言葉がどういう意味で使われているかによって、捉え方は大きく変わってきます。
骨盤の構造がどれほど安定しているのか。
そして、脚を組むという動作が、その構造にどんな影響を与えるのか。
それを理解すると、「脚を組むのはダメなのかどうか」の判断もわかってくるはずです。
骨盤は、簡単には歪まない
まず前提として知っておきたいのは、骨盤は非常に安定した構造を持っているということです。
骨盤は腸骨・仙骨・尾骨の骨から構成され、複数の靭帯と筋肉によって強固に支えられています。
座る、立つ、歩く、走るといった日常的な動きに対して、
骨盤は動きの中心として機能していますが、その形自体が大きく歪むことはありません。
解剖の実習に行った時に、ハンマーで叩いたり、大人2人がかりで引っ張ったりしたけど
びくとも動かなかったです。
仮に脚を組む程度の動作で骨盤が歪んでしまうのであれば、
階段を上がる、走る、荷物を持ち上げる──そんな当たり前の動作で毎回ズレてしまうことになります。
けど、そうしたこと起きていないですよね、骨盤の構造的にそんなに弱くはないんです。
骨盤の歪みを治しましょう、足を組んだら骨盤が歪みます!
とお話してる、整骨院や整体とかピラティスインストラクターとか
お見かけするけど、商売として言ってるのか、本当にそう思って言ってるのか不思議。。
「歪み」とは構造のズレではなく、機能の偏り
まず、「歪み」とは何を指しているのか。
よく使われてる「骨盤の歪み」という表現は、骨そのものがズレているというよりも
姿勢や筋肉の使い方のバランスが悪くなったり、関節の可動域に偏りができたり
機能的なアンバランスを指しているケースは見られます。
脚を組む動作は、その一因にはなりえます。
特に、いつも同じ脚を上にして組む習慣が続くと、股関節まわりの筋緊張や重心位置に偏りが生じ、
その結果として姿勢に歪みが出たように感じられる、ということはあります。

脚を組むことが問題なのではなく、組みたくなる状態にこそ注目する
脚を組むという動作そのものが、直ちに身体へ悪影響を及ぼすわけではありません。
座った姿勢の中で一時的に脚を組むのは、体勢を調整したり
快適さを求めて自然に行われる動きでもあります。
だけど、それがいつも同じ側で、同じ形で繰り返されているとすれば話は別。
習慣化されたいつもの動きの偏りは、身体の使い方に左右差を作ったり
筋肉や荷重の片寄りとして蓄積されていく可能性もあります。
それ以上に大事なのが、「なぜ脚を組みたくなるのか」ということ。
脚を組みたくなる原因には、骨盤が後傾している、あるいは坐骨でしっかりと座れていない
のような姿勢の不安定さが関係しています。
本来背骨が支えるべき体幹の安定性が損なわれ
身体は無意識に「脚を組むことでバランスを取ろう」とします。
一見リラックスしているようで、実際には姿勢の不安定さを補おうとしている感じ。
股関節の柔軟性や骨盤まわりの筋力に左右差がある場合、
「組みやすい側」「組みにくい側」が出てきて偏った習慣として固定されやすくなります。
脚を組むことがダメと捉えるよりも、そうなってる原因を見つける
大切なのは、「脚を組むかどうか」よりも、「自分の身体がどう動いているか」に意識を向けること。
必要に応じて調整できる視点と方法を持つことです。
身体は、偏っても戻れる構造を持っています。
その働きを信頼しながら、日々の中でどう動いているかを観察し、選択していくこと。
それが、快適な動きとバランスのとれた身体づくりの基盤になります。
TEL:090-7382-7539